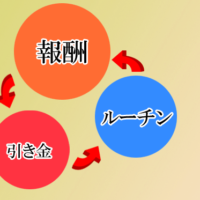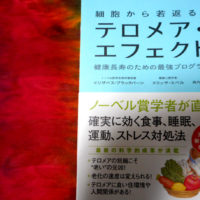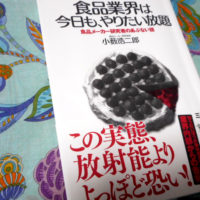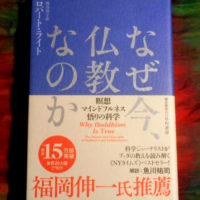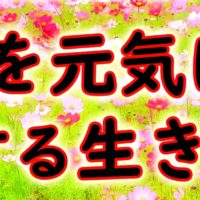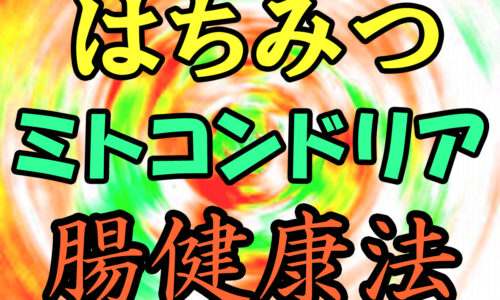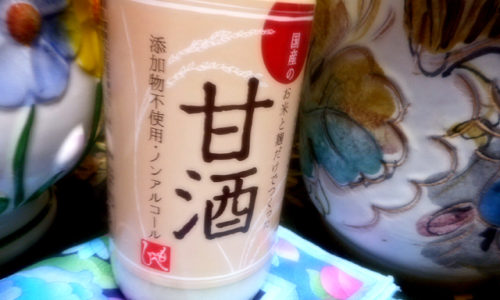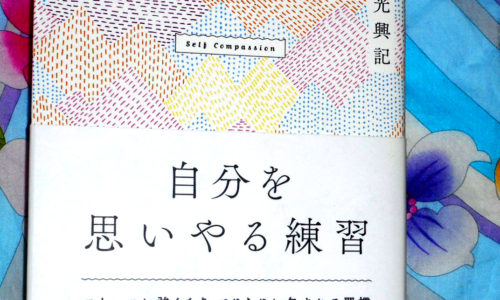contents
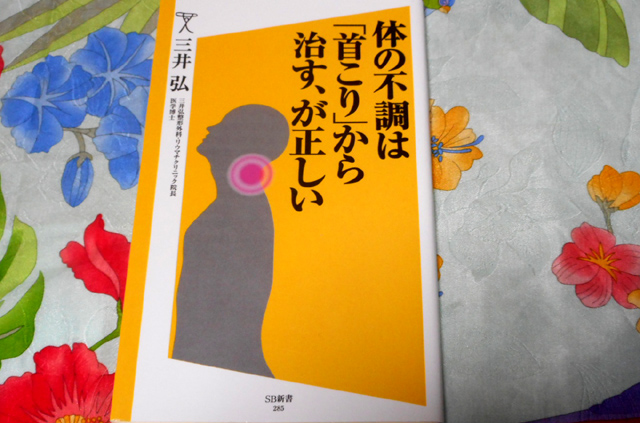
当ブログでは令和の時代のヘルスケア&セルフケアについて考えていますが、今回は『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』(三井弘 著 SB新書)という本をご紹介しながら、「首こり」の予防について考えていきたいと思います。
現代社会においては、スマートフォンをはじめとした携帯端末の普及や、オフィス内でパソコンを長時間使用する労働環境などによって、気づかないうちに首を酷使していると思われます。
しかし長時間、うつむいた姿勢を続けてしまうと、猫背になるのはもちろんのこと、首にも負担をかけてしまいます。そして気づかないうちに肩だけではなく、首もこってしまうのです。
これが「首こり」であり、「肩こり」とはまた違った症状だといわれています。
このことに関して、詳しく述べているのは、整形外科クリニックの院長をしている三井弘氏です。三井氏は、『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』(SB新書)のなかで、
休んでよくなるようなら、筋肉の緊張からくる「肩こり」と考えて差し支えはありません。
ところが、首の問題から「こり」が生じている場合は、何をやっても症状がよくならず、しつこいこりに悩まされます。休んでも取れない「しつこい肩こり」は、「首こり」からきていると考えたほうがよいのです。
「首こり」の場合、その主たる原因は、頸椎の変形で神経根が圧迫されたり、刺激されたりすることです。それによって「肩こり」を引き起こしているということですから、筋肉の緊張や疲労とは根本的に原因が異なります。
(三井弘『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』p58)
首の不調が起こるのは、首を酷使する生活が続くことが最大の要因です。
それでなくとも首は、日常生活の中で絶えず動かされ続けています。
(中略)
首が健康だからこそ、私たちはつつがなく日常生活を送ることができているのです。
しかし、そのことを意識することはほとんどありません。首がスムーズに動くことは、意識するまでもない〝当たり前〟のことだからです。
そのため必要以上に負担をかけてしまっても、よほどの症状が出ない限り、大概の人は首が傷んでいることに気づかないのです。
(三井弘『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』p23)
と述べています。
「首こり」はうつとも関係してくる。
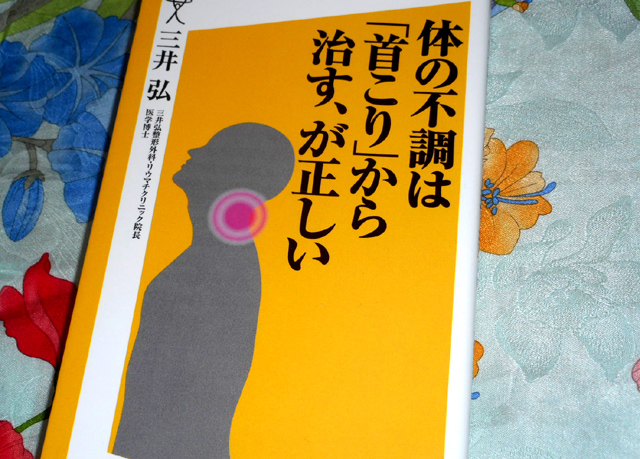
また、三井弘氏は、首に「必要以上に負担をかけてしまっても、よほどの症状が出ない限り、大概の人は首が傷んでいることに気づかない」と述べていますが、「肩こり」ではなく、知らない間に首がこってしまう「首こり」によって、からだに何らかの不調が引き起こされ、そのことによって、わたしたちの健康が損なわれてしまうことは十分考えられるのです。
特に「うつ」の症状や「うつ病」との関連性において、「うつは一般的に脳が関係しているとされていますが、その発症に、長時間にわたる首の酷使が関わっているケースもあるということです」と述べています。
さらに三井氏は、「首に不具合があると、その影響は首の動作だけに留まらず、全身の機能やメンタルヘルスにまで及びます」とし、
「なぜ「首」という1ヵ所が悪くなると、全身にまで影響が及んでしまうのか。その答えは明白です。私たちの生命を司る大切の器官が、首という細い場所に集中しているからにほかなりません」
としています。
つまり、首には脊髄や血管、食道、気管、甲状腺など、生命を維持するための器官が集中しているといいますので、からだとこころの健康を維持するためには、日頃から「首」を大切にするような生活習慣を心がけることが必要だと思われます。
首への負担を減らすには、あごを20度ぐらい上げる。

しかし首に溜まった疲労を取ろうとして、自分で首を間違った方向に急に動かしてしまうと、逆に首を痛めてしまうことにもなりかねません。
また先程も述べたように、首は生命を司るための大切な部位であると考えられるため、安易に首の辺りを自己流マッサージなどによって調整しようとするのも避けた方が良いと思われます。
そのため、この記事でも首の疲れをとるための具体的な方法については述べることが出来ませんが、『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』に書かれている、首の負担を減らすために、普段からあごを20度ぐらい上げることを心がけるという点は非常に参考になります。
正しい姿勢というと、あごを引くことをイメージしがちですが、三井氏は、「あごを20度ぐらい上げた状態」が首にとっての良い姿勢だというのです。
あごを引くと、頸椎は真っ直ぐな状態となり、重い頭を支えるためのカーブがなくなってしまいます。つまり、首が軽く前に突き出て、頭部が後方に位置するというバランスが取れなくなってしまうのです。
それによって頭全体の重さを受け止めて支えることができなくなり、首には余計な負担がかかってしまうことになります。
(三井弘『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』p109)
首を守るためには、頸椎のカーブを保てる姿勢であることが必要です。そのために最もよいのは、あごを20度ぐらい上げた状態です。要は、あごを少し上にツンと上げた姿勢です。これが首の骨のカーブに沿った「首にとっての正しい姿勢」なのです。
(同)
あごを引いてしまうことは、首にも大きな負担をかけるだけではなく、頸椎のカーブの消失によって、その下に続く胸椎や腰椎にも影響を与え、背骨全体の負荷も高めてしまいます。ですから、まずは「少しあごを上げる」を日頃から意識して生活してみてください。
立つときは、①あごを少し上げ、②胸を張り、③腰は少しそらし気味にして立つ、を心がけましょう。この姿勢を習慣にするだけで首こりの症状は相当改善されます。
(三井弘『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』p110)
あごを少しあげるようにする習慣をもつことで「首こり」予防。

したがって、テレビを見るときや本を読むとき、パソコンやスマートフォンなどを操作するとき、うつむきがちになるのを避け、意識的にあごを少しあげるようにしてみると、首への負担を減らせると思います。
また、テレビの位置を少し高くしたり、スマートフォンや本などを腕を動かすことで目線の方にもってきたりすることも、首に余計な負担をかけないようにするための工夫だといえます(私自身もこの本を読んだあとに、早速テレビの位置を少し高くしてみました)。
ほかにも、首に負担をかけないための、枕や椅子の選び方、食事や入浴の方法、「首を健康にする簡単トレーニング」など、日常生活のなかで首を守るための秘訣が、三井弘氏の『体の不調は「首こり」から治す、が正しい』のなかで数多く紹介されていますので、首への負担を少しでも減らしたい方は、ぜひ本書を読んでみてください。
うつの予防対策には、食事・運動・瞑想といった生活習慣が大切です。