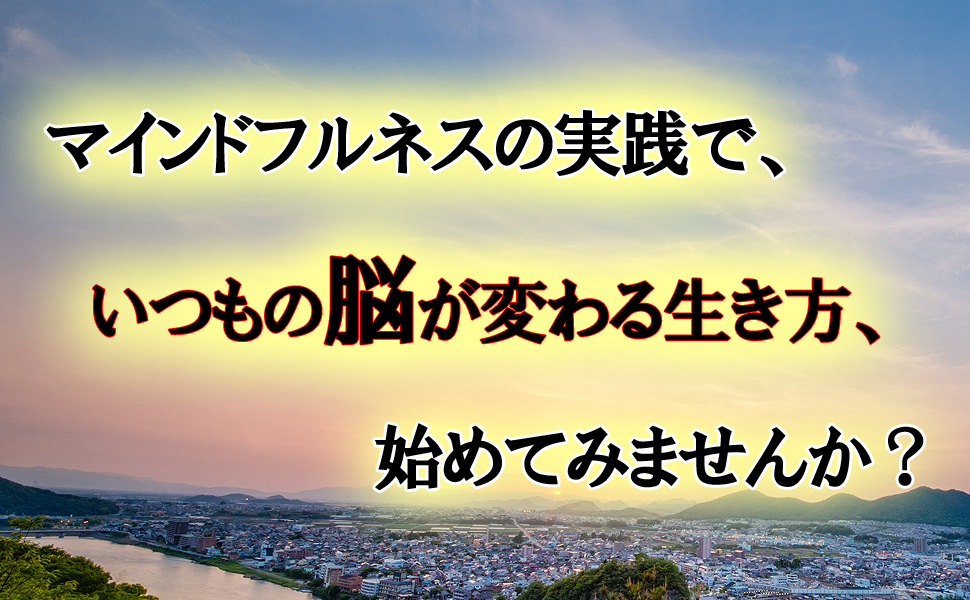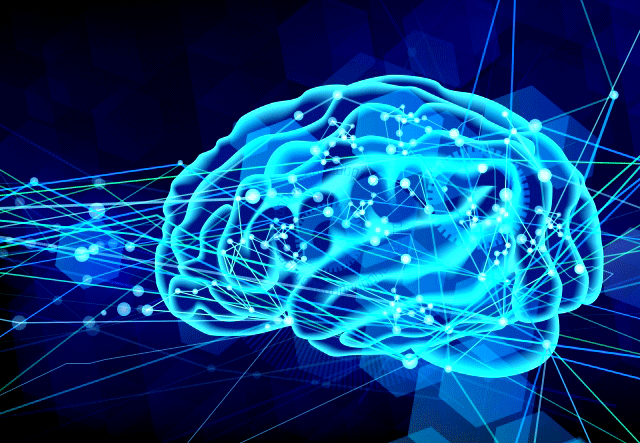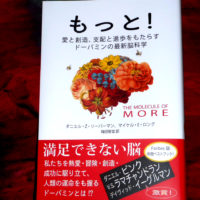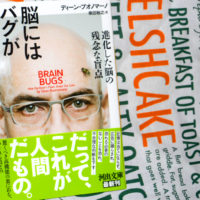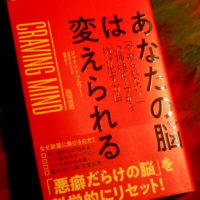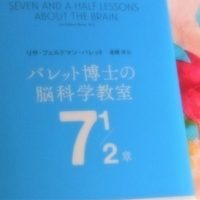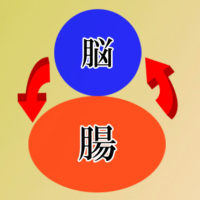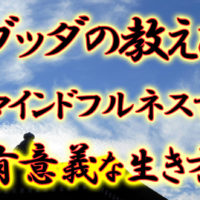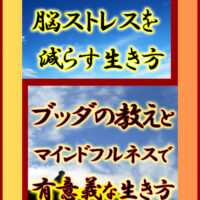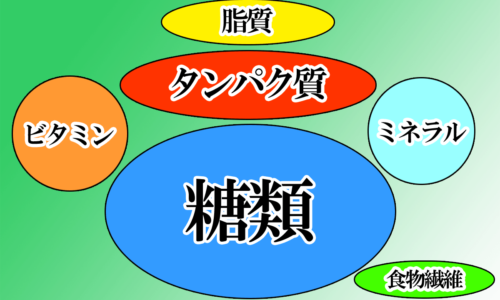contents

運動や瞑想などの習慣によって、いつもの脳は変えられる、ということはご存知でしょうか?
今回は、脳における神経可塑性についてです。
この記事でお伝えしたいことは、いつもとは違う動きをする運動を行なったり、マインドフルネス瞑想をしたりすることで、脳の神経細胞同士のネットワークを変えることができる、すなわち、いつもの脳は「鍛えることによって変えられる」ということです。
近年、脳科学ブームを筆頭に、「脳に良い/悪い」食べ物や行動など、「脳」の領域は、医療やビジネスの分野を含め、幅広い人々に関心が持たれるようになりました。
その「脳」とは一体何かといえば、まず、わたしたちの脳は約860億個の神経細胞(ニューロン)からできているとされています。
また、グリア細胞と呼ばれる多くの細胞が、陰の立役者として、神経細胞(ニューロン)の機能の一部を支えているといわれています。
そして、これまで、脳の細胞は生まれたときから減る一方だとされ、増えることはないとされてきましたが、脳は鍛えれば鍛えるほど、神経組織が活発になり、神経細胞同士の連絡が増えるなど、発達することが分かってきました。
つまり、日頃からの活動や経験によって、脳は自らの構造や機能を変えることができるのです。
このような、神経細胞同士のつながりが変わることは「神経可塑性」と呼ばれています。
一九九〇年代、神経科学は神経の可塑性とニューロンの新生に光を当て、脳についての見方を根本から変えた。まず神経の可塑性とは、脳は「プラスチック(可塑性物質)」で、鍛えることによって変えられることを意味する。従来、脳はいくつもの領域が配線でつながれた器官で、領域ごとに細胞とそのネットワークが決められた仕事をこなしていると考えられてきた。(中略)
じつのところ、脳は自ら配線をつなぎ替え、ほかの領域を代役にしてその仕事をこなすのだ。脳は適応し、成長することができる。これが「神経の可塑性」だ。
(ジョンJ.レイティ、リチャード・マニング『GO WILD 野生の体を取り戻せ!』 野中香方子 訳 p113)
運動や瞑想の習慣でいつもの脳は変えることができる。

たとえば、ゆっくりとしたヨガや気功などの運動をしたり、マインドフルネスや慈悲の瞑想をしたりすることで、脳の神経細胞同士のネットワークを変えることができるとされています。
そのため、毎日同じことを繰り返すなど、いつもと同じ生活をすることで脳をたいして使わなければ、そのぶん衰えていきますが、その一方で、たとえ加齢とともに認知機能が衰えたとしても、日々、脳が変化を感じるような生き方を志すなど、鍛え方次第で、結果は違ってくるのです。
(ただし、瞑想であれ、運動であれ、三日坊主で終わってしまうと、脳はいつもの「私」のいつもの「脳」に戻ってしまいます💦ので、新しいことを繰り返すことが重要です)。
以上ここまで脳の「神経可塑性」について述べてきましたが、うつや認知症などを予防したり、常日頃から心身ともにイキイキとした生活を送るためには、毎日の「習慣」を見直し、良いものに変えていくことが大切なのです。
神経可塑性の核心的な原理の一つは、「同時に発火するニューロンは互いの結合を強める」というものだ。これは、「心的な経験の繰り返しは、その経験を処理する諸ニューロン間の結合を強化することで、ニューロンの構造的変化をもたらす」ことを意味する。具体的には、何か新たなことを学習すれば、さまざまなニューロンのグループが結合を強める。
(ノーマン・ドイジ『脳はいかに治癒をもたらすか』 高橋 洋 訳 33頁)
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪
『マインドフルネス実践でいつもの「脳」が変わる生き方 もっと「今・ここ」を生きるための瞑想入門』Amazon Kindle で販売中です😊