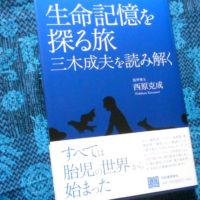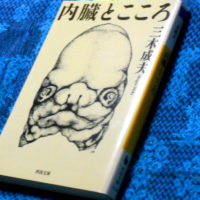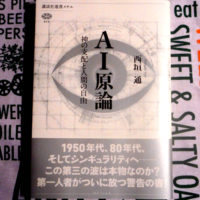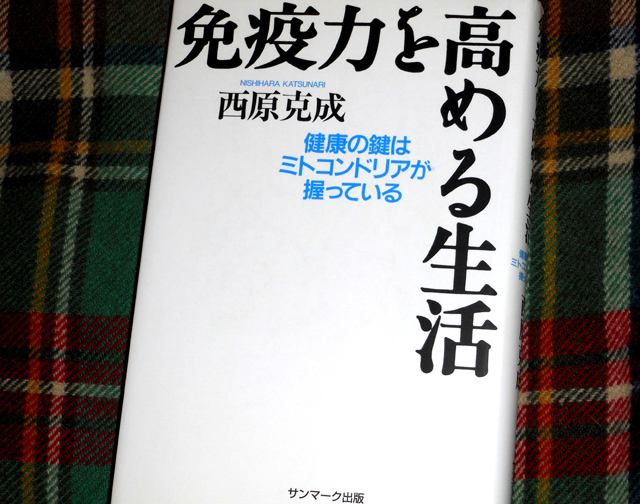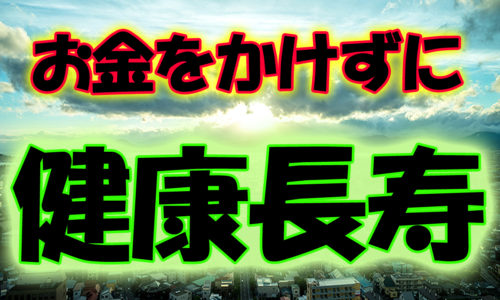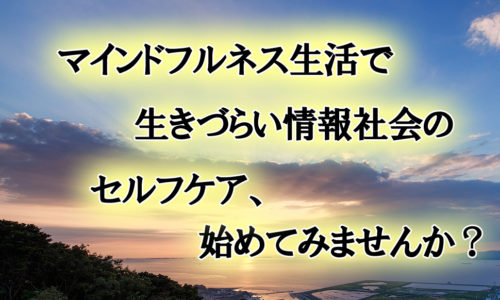contents

免疫力の要(かなめ)である腸の健康はいつも保たれていますか?
「脳」ともつながっている腸の腸内環境を良好に保つことは、毎日の健康や免疫力を維持していくために大切ですが、今回は、知っておきたい腸と進化の関係についてです。
腸はもともと、生物の進化の過程において生命の源であると同時に中心であると考えられています。
脊椎動物が誕生する以前に存在していた無脊椎動物の、たとえば「ホヤ」は、「原索動物」とも呼ばれ心臓や生殖器官を備えていますが、実は構造自体は、食物を消化・吸収するための簡単な消化管そのものなのです。
例えば、医学博士の西原克成氏は、以下のように述べています。
高等な多細胞生命体は腸の発生にはじまります。腸が無脊椎動物と脊椎動物を問わず、進化の出発点に発生します。多細胞生物は腸に外の物質を取り込み、これを消化し体内に吸収して細胞内で分解してエネルギーを取り出し、生命活動に供します。
(西原克成『内臓が生み出す心』)
また、医学博士の福土審氏は『内臓感覚 脳と腸の不思議な関係』のなかで次のように述べています。
進化から見ても、腸こそ、動物の最初の器官である。多細胞の動物の中でも最も単純な構造を持つものの代表が腔腸動物であり、ヒドラがこれにあたる。文字通り、腸が主体の動物だ。ここから、さまざまな形態に動物は進化していったのだが(略)、脳、脊椎、心臓がない動物はいても、腸がない動物はいない。
もう少し進化した動物は、たった一個の細胞である受精卵から発生する。受精卵が分割を繰り返し、器官を作れる程度に細胞が増えると、内側に細胞が管を作りながら伸びていき、身体の腹側に一本の管状の体を作る。これが腸である。腸の入り口は口、出口は肛門である。腸を包む外側の細胞群のうち、背側のものが板状になり、やがて、餃子状に身体の内側に落ち込んで別の管を作る。これが神経であり、やがて脊髄になる。こうして、最も外側の細胞群が身体全体を包み込む皮膚になる。皮膚になる細胞層との間にも細胞は増殖していき、やがて、筋肉や免疫系の細胞群を作る(略)。
(福土審『内臓感覚 脳と腸の不思議な関係』)
腸が進化したわけとは?
およそ5億年前には最初の脊椎動物であるヤツメウナギなどの無顎類が誕生し、その後、魚類、両生類、爬虫類と進化していくにつれて、腸の構造もより高度なものに変化していくようになります。
無顎類の腸は単純管状ですが、魚類になると胃が出現し、両生類になると大腸が備わるようになります。
そのように腸が進化した理由は、生活環境が海から陸へと移ることによって食の種類が劇的に変化したことで、消化器の形態に大きな影響を与えたからだと考えられています。
大腸が出現した理由とは?

また、大腸が出現したのは、陸上生活への移行によって水分不足に陥らないよう、小腸で吸収される水分をさらに徹底して吸収するためだと言われています。
このことに加えて、排泄物を垂れ流しにしないように一時的に大腸に溜めておくことによって、捕食者から気づかれないようにすることも、大腸が出現した大きな理由のひとつとして挙げられています。
そして、爬虫類から哺乳類へと進化するようになると、消化管はより複雑化し、長さも増していくようになります。
そこからさらにヒトが誕生するようになると、その食性は「超雑食」といえるような多岐にわたるものになっていき、それに伴って消化器官である腸も、消化の機能を複雑化させるだけではなく、細菌やウイルスの侵入を防ぐために高度な免疫システムまでをも備えるようになったとされています。
以上が、腸と進化の関係についてです。
<生命の主人公は、あくまで食と性を営む内臓系で、感覚と運動にたずさわる体壁系は、文字通り手足に過ぎない、ということです。>(三木成夫『内臓とこころ』)
参考文献
上野川修一 『からだの中の外界 腸のふしぎ』 講談社
三木成夫 『内臓とこころ』 河出書房新社
西原克成 『内臓が生みだす心』 NHK出版
福土審『内臓感覚 脳と腸の不思議な関係』 NHK出版
藤田紘一郎 『脳はバカ、腸はかしこい』 三五館