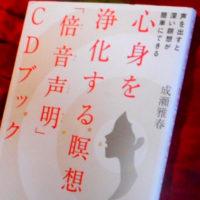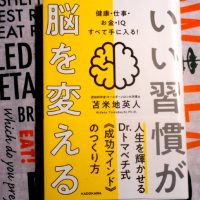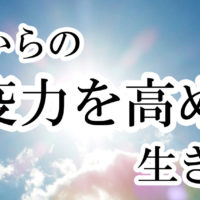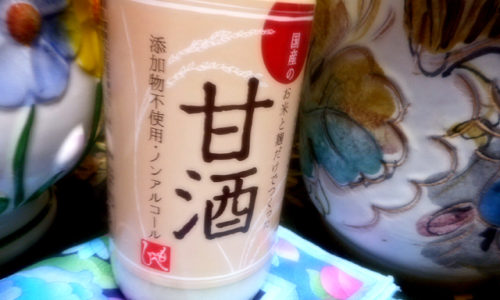contents

最近なんだかメンタルが不調……元気がでなくて「うつ」っぽいと感じたら、うつな気分を少しでもやわらげるために、1分間のマインドフルネス瞑想を生活にとりいれてみませんか?
今回は1分間のマインドフルネス瞑想がうつを遠ざける理由についてです。
以前の記事でうつの改善のために瞑想が効果的な理由について書きました。
しかし、うつの症状をやわらげるために初めて瞑想をしてみても、なかなか集中力が続かない、という方は多いと思います。
また、瞑想を始めても、すぐに頭の中に様々な考えや雑念が浮かんできてしまうということも十分考えられます。
ですが、だからといって落胆して瞑想をあきらめてしまう必要はありません。
なぜなら瞑想によってうつを改善していくために大切なのは、瞑想がうまくいくことではなく、心のトレーニングとしての瞑想を行う習慣をもつということだからです。
そのため、なかなか集中力が続かなかったり、すぐに雑念が浮かんで気が散ったりしても、失敗したと思って自分を責めることはないのです。
さらに、瞑想を行うことで、無理に幸せになろうとする必要もありません。
瞑想で大切なのは、何と言っても、出来事や物事に対して、自分の見方で判断したり評価したりせず、自分の考えをいったん宙づりにしてあるがままを受け入れること、今起きていることに「気づく」こと、観察することです。
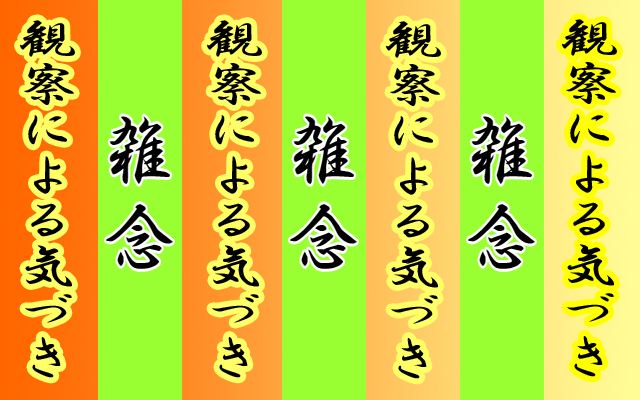
そしてそのことを心のトレーニングとして繰り返し、毎日の生活習慣にしていくことです。
『1分間瞑想法』の吉田昌生氏による言及
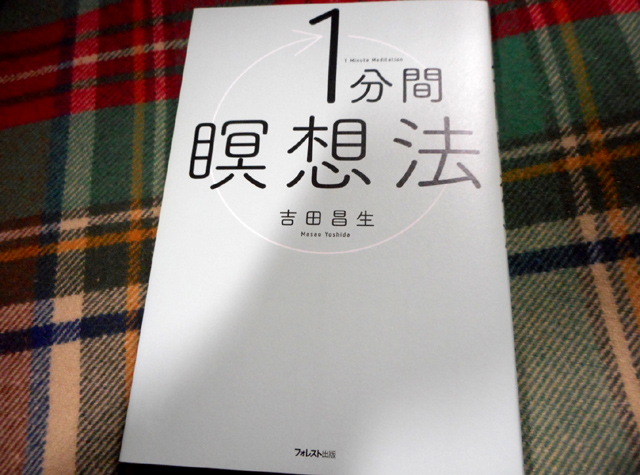
例えばこのことに関して、ヨガ・瞑想講師の吉田昌生氏は『1分間瞑想法』のなかで以下のように述べています。
瞑想と聞くと、多くの人が「『無』にならなければならない」と思うようですが、必ずしもそうではありません。
マインドフルネスの目的は「気づく」ことです。
「気づき」が連続することで「無」になることはありますが、「無」になることが目的ではありません。雑念が湧いても、それに気づいて、再び集中すればいいのです。
瞑想で大切なことは、次の2つです。
- 感覚に集中すること
- 集中に途切れたことに気づくこと
(吉田昌生『1分間瞑想法』p54)
まず注意を向けること、そこから注意がそれたら戻すこと、この繰り返しによって、脳が鍛えられていきます。
このトレーニングを繰り返すことで、脳が普段働いていないところに血液を送り込み、低下していた機能を取り戻すことができます。
だから、雑念が湧いてもいいのです。
雑念が湧いたことに「気づく」ことで、それが「負荷」になって、脳が鍛えられていると捉えてください。
(吉田昌生『1分間瞑想法』p55)
そして、この記事では、初めての方にオススメの瞑想法として、吉田昌生氏の『1分間瞑想法』から、「聴覚瞑想」を紹介したいと思います。
- 注意を音に向ける
- 近くの音に耳を澄ます
- 遠くの音の音に耳を澄ます
- 音と音の間にある静寂にも耳を澄ます
コツは、今この瞬間の音にすべての注意を向けることです。そして、聞こえてくる音を判断せず、快不快に分けたり、分析したりしないで、あるのまま受信してみましょう。
空気の振動のみを感じとり、鼓膜だけでなく、身体全体で音を感じとってみてください。
(吉田昌生『1分間瞑想法』p60~61)
うつ対策のために日頃から1分間のマインドフルネス瞑想を行うようにしてみる。

世界は様々な音で溢れ返っていますので、まずは呼吸や音を感じる瞑想を1分間で良いので、続けてみてください。
もし騒音などが不快に感じる場合は、自然のなかに身を置き、小鳥のさえずりや風の音などに対して耳を澄ましてみてください。
自然音には非常に高いリラックス効果とストレス解消効果があります。
また、他の記事で述べましたが、近頃は自然の姿を撮影したYouTube動画が充実していますので、外に出られないという方は、そのようなYouTube動画を利用してみるのもオススメです。
さらに、日常生活のなかのストレスで、イライラしたり、モヤモヤしたり、緊張したりしたら、その度に1分間、自分の呼吸に気づく瞑想を行う習慣をもつことも、ストレス対策や心の健康を保つためにおすすめです。
以上、ここまで1分間のマインドフルネス瞑想がうつを遠ざける理由について書いてきましたが、日頃から1分間のマインドフルネス瞑想を行うようにしてみることは、うつ対策のために非常にお勧めです。
もし、1分間が長いと感じる方は、まずは10秒から始めてみるのも良いと思います。
なお、詳しいマインドフルネス瞑想の方法についてはこちらの記事をご参照ください。
うつの予防対策には、食事・運動・瞑想といった生活習慣が大切です。

当ブログ管理人が書いた『食事・運動・瞑想で「うつ」な気分をよくする生き方 自分を大切にするためのセルフケア習慣』、Amazon Kindleで販売中です(^^♪