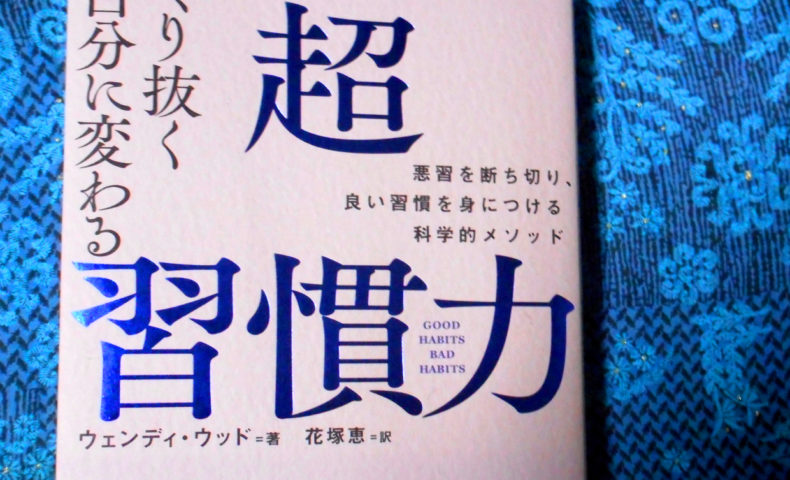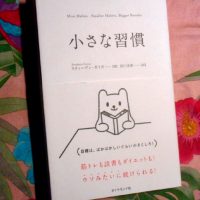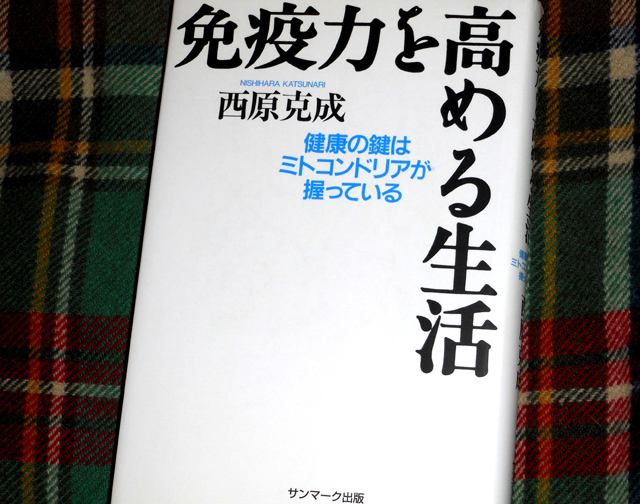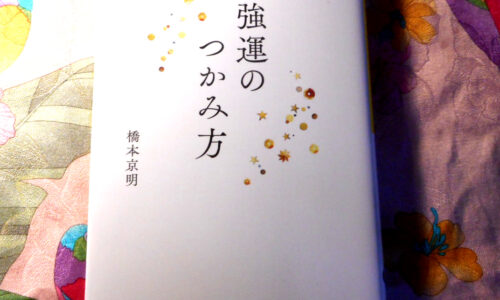2023年の新生活は、これまでの習慣を見直し、運動や瞑想など、良い習慣を始めてみませんか?
今回の記事では、ついやってしまう「習慣化」の鍵を握るのは「状況」と「きっかけ」であるということについて述べていこうと思います。
以前の記事で、「習慣化」とは、繰り返すたびに脳の神経回路が強化され、「自動作業」や「自動操縦」のごとく、いちいち意識しなくても、勝手にやってしまう行動のことであると述べました。
すなわち習慣化に成功すれば、いちいち決断しなくても、もしくは他人に促されなくても、勝手にやってしまうのです。
このことについて、たとえばアメリカの作家であるグレッチェン・ルービン氏は、『人生を変える習慣のつくり方』のなかで、「決断という行為がなくなることで習慣となる」と述べています。
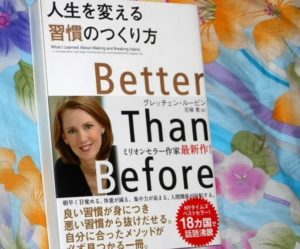
習慣となっていることをするのに、決断は必要ない。その決断はすでにされている。朝起きたら歯を磨く、薬を飲むといったことは、すでに決めていることだから、わざわざ決断しない。すでに意識していることだから、無意識に行う。理にかなった選択かどうかを心配することもない。最初に理にかなった選択をすれば、その後、選択する必要はなくなる。
(グレッチェン・ルービン『人生を変える習慣のつくり方』 花塚恵 訳 14頁)
また、南カリフォルニア大学心理学部教授であるウェンディ・ウッド氏は、『やり抜く自分に変わる 超習慣力』(花塚恵 訳)のなかで、
パターンとして形成された行動が、多くの人が信じているように「とにかくやる」ことの産物であるなら、毎日欠かさず行うと決めているのは、私たちの顕在意識になるはずだ。
としながらも、
顕在意識は自分がとるどんな行動ともほとんど接点がない。習慣的な行動となればなおさらだ。行動するときに機能するのは、離れているも同然の膨大な潜在意識だ。
と説明しています。
そして、
「自分の目標に即した良い習慣も、目標を阻害する悪い習慣も、習得のメカニズムはまったく同じだ。良い、悪いにかかわらず、習慣の起点は変わらない」
と述べています。
これはどういうことかといえば、たとえば、退屈になるとつい手元にあるスマートフォンでSNSをチェックしたり、寝る前にダラダラとユーチューブで動画を見てしまったりすることはよくあることかもしれませんが、そのことと、毎日健康のために早起きしてウォーキングやジョギングをすることは、「習慣の起点」という観点からはほとんど変わらないということです。
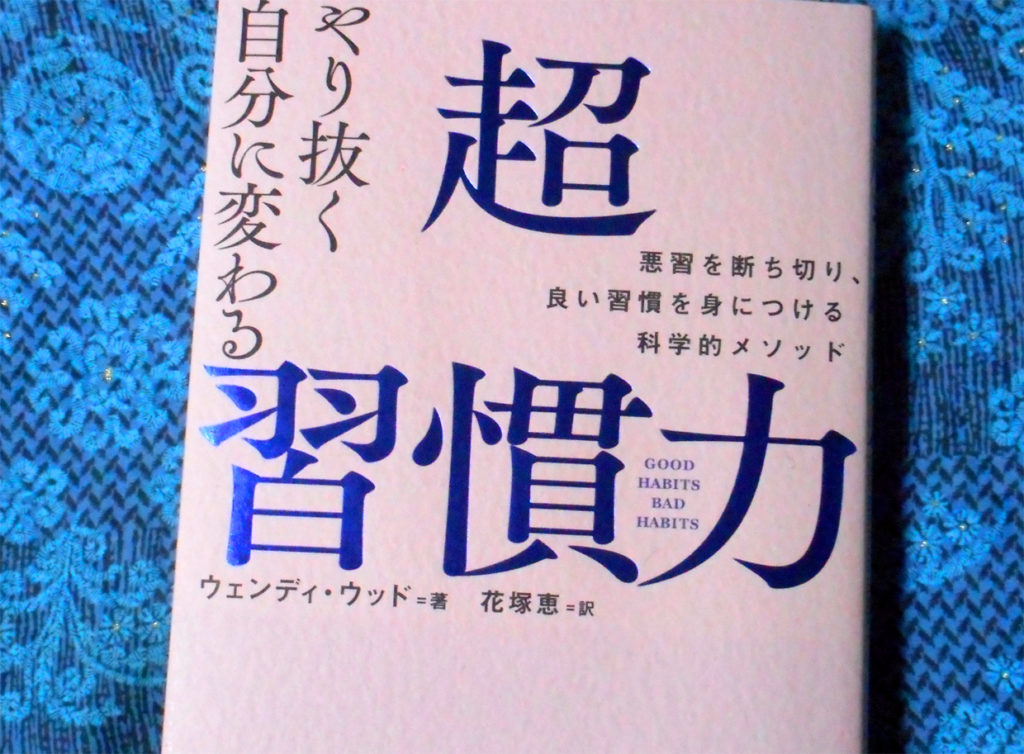
さらにウェンディ・ウッド氏は、
「同じ行動を繰り返せば、その行動に対する意識の仕方が変わる。最初は動機を持って始めた行動(健康維持などの目標を達成するために始めた行動)が、繰り返すうちにその行動をとる状況と反応が強く関連づけられ、習慣となる」
「習慣は、状況がもたらす合図と、その状況で報酬のためにとる行動を繰り返すなかで身につく反応が、意識上で関連づけられたときに作用する」
「努力が不要であるという性質は、習慣を決定づける性質のひとつだ」
とも述べています。
これはどういうことかといえば、「習慣化」の鍵を握るのは、「繰り返し」や「状況」であるということです。
自分にとって悪い習慣を絶ち、良い習慣をスタートさせるためには、「決断」や「努力」は最初のうちは必要かもしれませんが、良くも悪くも続けることで一度習慣になってしまえば、わざわざやる気を起こさなくても、そういうものとして勝手にやってしまうのです。
たとえば、いつもの習慣として退屈な時についスマホをいじってしまうのは、「退屈である」と同時に、手元にスマホが置いてある状況に自分自身が置かれているからです。もしスマホでSNSをチェックするよりももっと楽しいことがあればそのことに集中するのであり、また、もしスマホが手の届かない所にあれば、そもそもスマホをいじることは出来ないのです。
もしウォーキングやジョギングを健康のために毎朝の習慣にしたいのであれば、いつもより早起きすることで時間にゆとりがあることや、通勤・通学の途中に運動できる場所(公園など)が視界に入るかどうか、といったことが重要になってくるのです。
そして朝に運動することが「気持ちいい」「体調がいい」と感じられ、そのことが自分自身にとっての報酬や価値になれば、繰り返し実践しようと思えるのです。
すなわち「繰り返すうちにその行動をとる状況と反応が強く関連づけられ、習慣となる」のです。
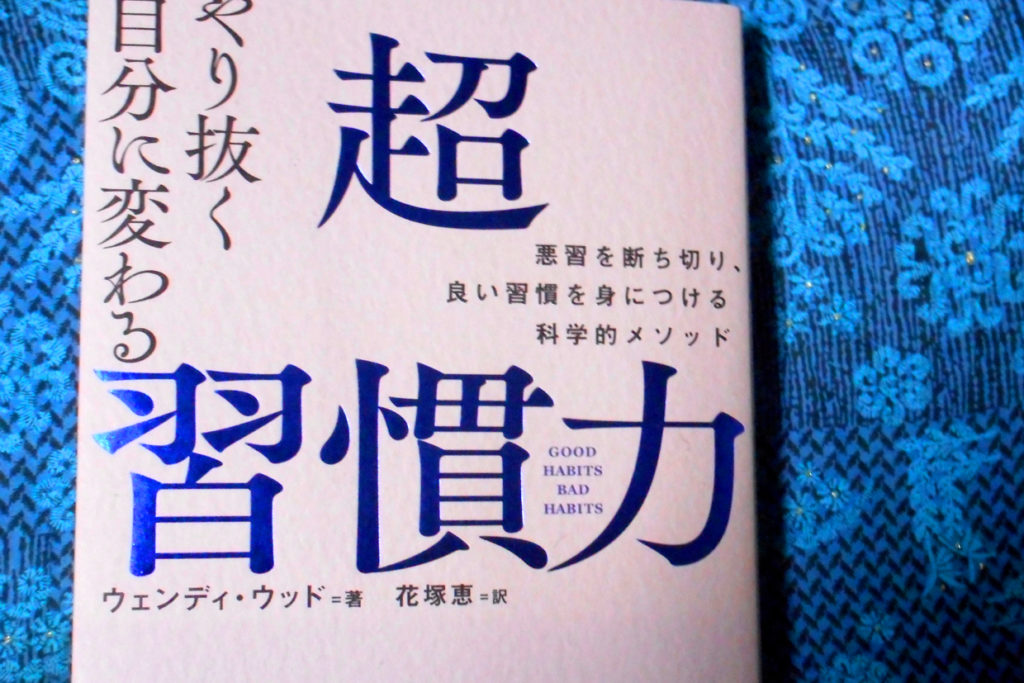
思考のスピードは、習慣が支配力を得るカギを握る。同じ行動を繰り返せば、その行動に対する意識の仕方が変わる。最初は動機を持って始めた行動(健康維持などの目標を達成するために始めた行動)が、繰り返すうちにその行動をとる状況と反応が強く関連づけられ、習慣となるのだ。その状況を思い浮かべると、直ちに意識が反応するようになる。意識にのぼるスピードが上がれば、ゆっくり考えようとする顕在意識が別のことをやろうか決めかねているうちに、習慣となっている行動をとる準備が整う。
(ウェンディ・ウッド『やり抜く自分に変わる 超習慣力』 花塚恵 訳 85頁)
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪
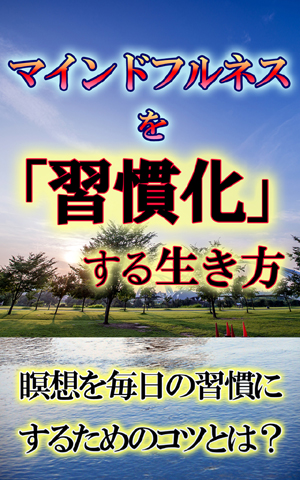
マインドフルネス習慣シリーズ第1弾、『マインドフルネスを「習慣化」する生き方 瞑想を続けるための3つの方法』
Amazon Kindle で販売中です😊