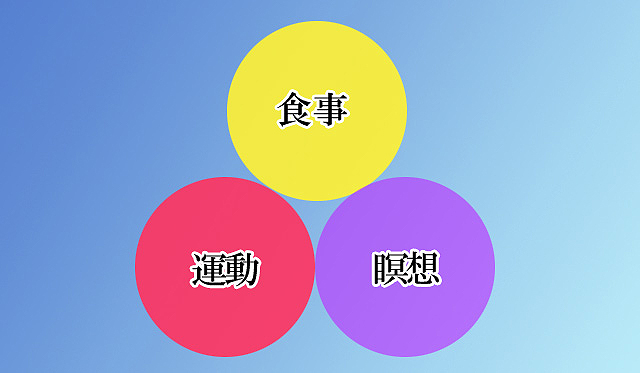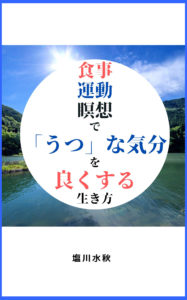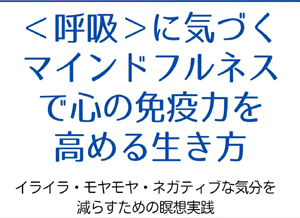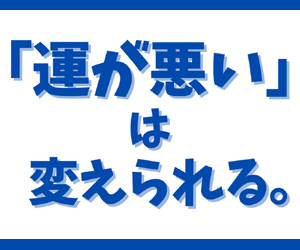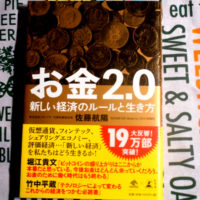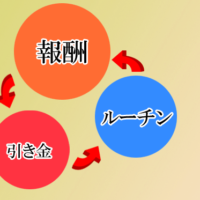contents

天然はちみつをうつの予防対策に役立ててみませんか?
当ブログでは主に、ハチミツとミトコンドリアで真の健康を実現する方法について書いていますが、今回は天然・生のハチミツがうつの予防対策に役立つわけについて述べていきたいと思います。
蜂蜜は古来、万能薬として利用されてきましたが、うつの予防や対策のためにも効果を発揮してくれる食材なのでしょうか?
たとえば、ルーシー・M・ロングの『ハチミツの歴史』 (大山 晶 訳)には、
「ハチミツは薬の苦さをこまかしたりのどの痛みを鎮めたりするだけでなく、それ自体が薬として使われることも多い。健康上のさまざまな理由により、昔から世界中で使われてきた。病気や災難を遠ざけるお守り、薬剤、抗うつ剤、一般的な強壮剤、力の源、さらには肌や髪の美容液として利用されてきたのである」
という記述があります。
しかし、はちみつがうつを予防したり、緩和したりすることについては、あまり話題に上らないような気がします。ですが、私自身は、栄養バランスが整った非加熱の天然・生はちみつをうまく食生活に採り入れることは、うつの予防や対策のために効果的だと考えています。
その理由は、加工食品に含まれる異性化糖(ブドウ糖果糖液糖)や人工甘味料などを止める「ゆるやかな糖質制限」と、「腸内環境を整える」ことが、うつの予防や改善につながると、私自身、考えているからです。
そして非加熱・無添加の生ハチミツは、その二つに有効なのです。
はちみつがうつの予防に効果的なワケ
うつとゆるやかな糖質制限の関係。

うつの症状を予防したり、緩和したりするためには、ゆるやかな糖質制限が大切になってくるように思います。しかしここでいう「糖質制限」とは、極端にごはんやパンなどに含まれる炭水化物を減らして、なるべく糖質の摂取量をゼロに近づけることではありません。
それよりも、白砂糖や果糖ブドウ糖液糖、異性化糖、など急激に血糖値を上げる糖質を減らすことが重要になってくるように思います。
なぜなら白砂糖やブドウ糖果糖液糖などは、インスリンの過剰な分泌によって血糖値を乱高下させ(インスリン・スパイク)、精神を不安定にさせるといわれているからです。
このことに関しては、たとえば薬学博士の生田哲氏は以下のように述べています。
血糖値をうまくコントロールできない状況、言い換えれば、血糖値の上がり下がりが激しい状況を血糖代謝異常(低血糖症)と呼んでいる。血糖代謝異常のおもな症状は、朝起きられない、強い疲労感、気分の落ち込み(うつ症状)、気分のコントロールがきかない、集中力の欠如、物忘れがひどい、イライラ、突然の怒り(キレる)、めまい、ふらつき、悪夢、夢遊病、眠っている間に話す、不安、恐れ、震えなどである。
(生田哲『食べ物を変えれば脳が変わる』p120)
砂糖や砂糖のように高度に精製されたカーボは、脳内の伝達物質に働きかけるばかりでなく、血糖に大きな影響をおよぼします。甘いものを食べると伝達物質レベ ルと血糖がいっしょに上がり、一時的な陶酔感や快感が得られますが、つぎに、両方とも下がります。こうして気分が落ち込み、元気がなくなります。これがうつです。
(生田哲『砂糖をやめればうつにならない』p103)
そのため、うつの予防対策のためには、血糖値を急激に上げてしまう糖質をなるべく控えていくことが大事だと考えられるのです。
しかし、糖質は、脳や身体の大切なエネルギー源であるため、脳や身体が必要としている分は、しっかりと摂っていかなければならないように思われます。
アカシア蜂蜜などのハチミツは血糖値を上げにくい。

そこで、糖質を摂る際は、血糖値を急激に上げない「低GI」の食品を選んでいく必要があるのですが、蜂蜜のうち、特にブドウ糖よりも果糖のほうが多いハチミツ(アカシア蜂蜜・ジャラハニーなど)は、血糖値を上げにくいとされています。
さらに、ミツバチの酵素のちからによって、糖類が最初から果糖とブドウ糖に分離しているため、吸収されやすく、エネルギーになりやすいとされています。
そのため蜂蜜は、GI値が高い白砂糖や人工甘味料を止める、ゆるやかな糖質制限のお伴にオススメです。
しかし、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで数百円で販売されている蜂蜜の多くは、「純粋」と表記してあっても、加熱されていたり、水アメなどが混ざっていたりする可能性があるため、うつの予防対策のためにハチミツを利用する際は、非加熱・無添加のものを選ぶ必要があります。
うつの予防対策には腸内環境を整えることも必要。

また、腸内環境を良くすることも、うつの症状を予防したり、緩和したりすることにつながっていくと思われます。
その理由は、腸内環境の良し悪しと心の状態は密接につながっていると考えられるからです。
腸は脳と神経系でつながっているため、心理的ストレスによって脳が不快を感じると、腸でも悪玉菌が増殖するなどして、腸内環境が悪化します(「脳腸相関」)。また日頃の生活習慣による腸内環境の状態の良し悪しも、脳の「快」「不快」に関係してきます。(「腸脳相関」)。
すなわち腸は「第2の脳(セカンドブレイン)」と言われているほど、脳と互いに関係し合っているのです。
また、一般的にうつの症状にはセロトニン不足が関係していると言われていますが、実はこのセロトニンとは、もともと腸内細菌間の伝達物質であり、その約90%が腸内に存在しているのです。
つまり、セロトニンのほとんどが腸で作られているのです。
このことに関して、例えば、医学博士の藤田紘一郎氏は以下のように述べています。
最近私は、腸内環境の悪化がうつ病や不安神経症を促している可能性を示唆する研究結果を発表しました。脳の健康は腸の健康であると同時に、腸の健康は脳の健康であると考えられるようになったのです。幸せ物質であるセロトニンが90%腸に存在していることは何度も述べました。腸内に危険な物質が入ってくると、腸内のセロトニンが働いて脳に危険な物質を胃から吐き出せと命令を出させると同時に、脳を介せず下痢という手段で体内から危険な物質を排泄しようとします。
このように腸から指令がなくても、独自のネットワークによって命令を発信する機能を持っているのは、臓器の中でも腸だけです。腸のセロトニンの働きが心の健康にも重要な影響を与えているということです。
(藤田紘一郎『脳はバカ、腸はかしこい』p82)
ハチミツには腸内環境を整える働きがある。
昔からはちみつには整腸作用があるといわれており、インドの伝統医学である「アーユルヴェーダ」でも、蜂蜜は軽い便秘薬として利用されてきたといいます。
実際、蜂蜜には腸内細菌のバランスを整え、腸内フローラを元気にするのを助けてくれるオリゴ糖やグルコン酸などが含まれています。
そのため、ひとさじのはちみつをなめることは、腸内環境を整えるのに効果的なのですが、整腸作用のあるヨーグルトやアロエベラなどと組み合わせるのもオススメです。
また、ニュージーランドのマヌカハニーやオーストラリアのジャラハニーには、一般的なハチミツよりも腸内細菌のバランスを整える働きがあるとされています。
栄養豊富なハチミツは身体と心を元気にしてくれる。
以上、ここまで天然・生のはちみつがうつの予防や対策に役立つ理由について述べてきましたが、非加熱・無添加の蜂蜜には、活性型のビタミンやミネラル、アミノ酸、有機酸、酵素など、からだとこころを元気にするための栄養素がバランスよく含まれています。
もちろん、そのハチミツを舐めれば、うつがみるみるうちに治るわけではないかもしれませんし、うつを予防するためには、日頃から適度に運動したり、心のトレーニングとして瞑想したりすることも必要だと思います。
しかし、毎日の食事を見直し、それと同時に、寝る前と起きた時に、ひとさじのはちみつを舐めるようにするなど、日々の食習慣に蜂蜜をプラスしてみることは、心の健康維持のために役立つと思うのです。
うつの予防対策には、食事・運動・瞑想といった生活習慣が大切です。