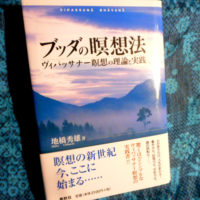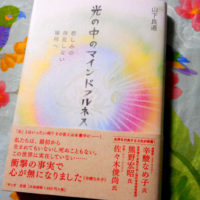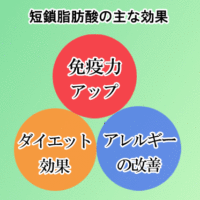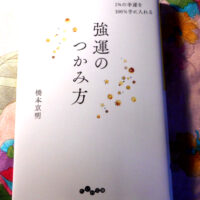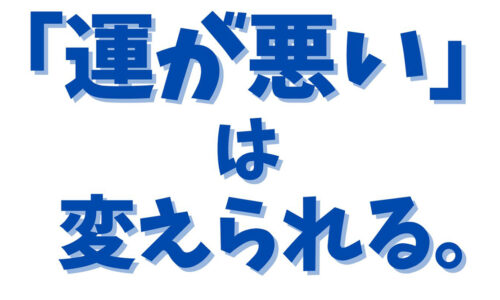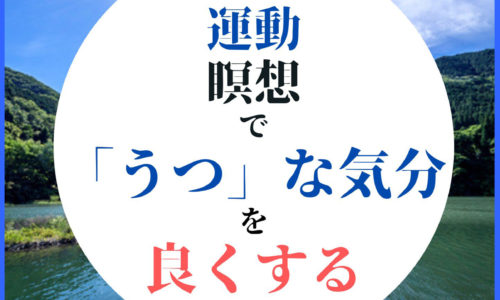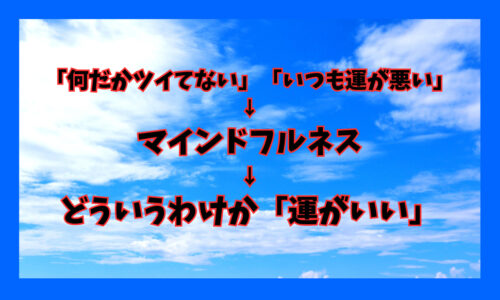contents
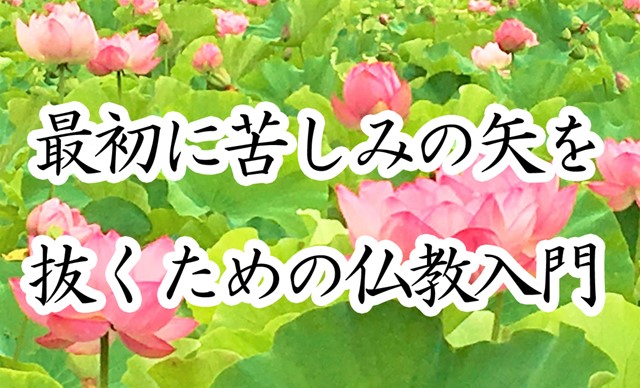
コロナ禍の日々がつらい、苦しいという時こそ、ブッダの智恵で気持ちをラクにする生き方、始めてみませんか? 今回の記事では、心の苦しみや生きづらさを少しでも減らしていくためにブッダの教え「無我」について述べていきたいと思います。
前回の記事はブッダの重要な教え「無常・苦・無我」のうち、「無常」を取り上げました。今回は「無我」についてです。
「無我」とは、明確に自己と呼べるような本質や実体を持たないということです。別の言い方をすれば、常に「私」は同一ではない、つまり、変わらない「自己」はないということです。
そもそも体を構成する細胞は常に代謝によって入れ替わっているため、昨日の私と今日の私は決して同じではありません。
また自分という存在を定義する場合には、年齢は幾つか、性別は男性か女性か、どこに住んでいるか、どの学校や会社に属しているか、食べ物は何が好きか、などを挙げると思われますが、5年後や10年後、学校を卒業したり会社を辞めたりしていれば、自分の定義も変わってきます。
さらに、数年後には趣味や嗜好なども変わっているかもしれません。
そういう意味では常に同一の「私」というものは存在していないと言えるのですが、「私」という言葉や自分の名前(固有名詞)は変化しないため、昨日の自分と今日の自分は同じであるように錯覚してしまいます。
また、歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏がいうように、「私たちのほとんどは、自分を物語る自己と同一視する。私たちが「私」と言うときには、自分がたどる一連の経験の奔流ではなく、頭の中にある物語を指している」のです(注1)。
「私」は変化し続けている。

もちろん、いつも変わらない自分の名前は他者から承認されるために必要不可欠ですし、昨日と今日の「私」は同じであるという、一貫した「自己」があるという前提も、日常生活を送るうえでは無いと困るものです。
しかしその一方で、環境との関わりによって「私」が変化し続けているという視点を持つことも重要であるように思います。
たとえば〈自分探し〉のために「いつもの日常」というしがらみから離れて海外を旅行してみれば、そこで見つかるのは本当の自分や本来の自分ではなく、新しい環境との関係性のなかで変わっていく新しい自分なのです。
一方、「自分は常にこういう存在だ」と決めつけ、何でも自分にこだわりすぎると、他者との関係性においては(融通が利かないという意味で)非常に生きづらくなります。
ちなみに「無我」というと、自我(エゴ)を無くすことだと思われがちですが、「無我」については、「非我」(「我」に非ず)という翻訳のほうがより精確であるように思われます。
このことに関して中村元・田辺祥二氏らは『ブッダの人と思想』のなかで、原始仏教の時代においては、「無我」ではなく「非我」が説かれていたとし、
ブッダは、自己にあらざるものを自己とみることによって、苦しみが生じると説きました。つまり、ブッダの言わんとすることは、まず、自己にあらざるものを自己の所有とみなすこと、二つには、自己には常住不変の実体があるとみなすこと、三つには自己の本質というものがあるとみること、これらを否定することが非我の内容であると説きます。
と述べています。
ブッダが「無我」を説いた理由とは?

ではなぜブッダが「無我」の教えを説いたのかといえば、インドでは「アートマン」(我)と「ブラフマン」(梵 宇宙の根本原理)の二つが、変わることのない絶対的な実体として存在すると考えられていたからです。
すなわち「無我」(非我)においては、自分に属していないものを自分のものと見なしてしまうこと、常に変わらない「私」という実体があること、さらに自己に常住不変の「アートマン」といった本質があることが否定されているのです。
しかし「ブッダは、人間存在は非我(無我)であるかといって、自己の存在を否定したわけではありません。むしろ倫理的行為の主体として、自己の存在を積極的に肯定していました」と述べられているとおり、ブッダは自己そのものを完全に否定しているわけではありません(注2)。
つまり、自己が「ある」か「ない」か、どちらかを選ぶということではなく、ブッダのいう「自己」とは、「縁起」の考え方と同様、関係性によって成立するものであると考えられるのです(注3)。
すなわち「無我」について考える時は、自己が「ある」か「ない」かということではなく、「他の諸々の現象と同様に、無常であり、因縁によって生じているもの」であるという〈プロセスとしての自己〉と捉えたほうが良いと思われます(注4)。
ブッダは、私たちが自己の一部だと考えるものの無常性を説いた。思考、感情、態度が無常であり、たえず生滅し変化するのもやはり、変化しつづける力が私たちに作用し、私たちの内面に連鎖反応を引き起こした結果だ。私たちの内面は原因や条件にもとづいている。そして条件が変化すれば条件づけられたものはすべて変化をまぬかれない。しかも条件はほとんどつねに変化している。
(ロバート・ライト『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』 熊谷淳子 訳 269‐270頁)
注1 『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来』下 ユヴァル・ノア・ハラリ 著 柴田裕之訳 河出書房新社
私たちのほとんどは、自分を物語る自己と同一視する。私たちが「私」と言うときには、自分がたどる一連の経験の奔流ではなく、頭の中にある物語を指している。混沌としてわけのわからない人生を取り上げて、そこから一見すると筋が通っていて首尾一貫した作り話を紡ぎ出す内なるシステムを、私たちは自分と同一視する。話の筋は嘘と脱落だらけであろうと、何度となく書き直されて、今日の物語が昨日の物語と完全に矛盾していようと、かまいはしない。重要なのは、私たちには生まれてから死ぬまで(そして、ことによるとその先まで)変わることのない単一のアイデンティティがあるという感じをつねに維持することだ。これが、私は分割不能の個人である、私には明確で一貫した内なる声があって、この世界全体に意味を提供しているという、自由主義の疑わしい信念を生じさせたのだ。(124頁)
注2 『ブッダの人と思想』 中村元、田辺祥二 著 NHKブックス
注3 『ブッダが説いたこと』 ワールポラ・ラーフラ 著 今枝由郎 訳 岩波文庫
ブッダの教えによれば、「私には自己がない」という考えも、「私は自己をもっている」という考えも、ともに間違っている。なぜなら、両者ともに「私は存在する」という誤った感覚から生起する足枷だからである。アナッタ(無我)の問題に対する見解は、いかなる見解にも見方にも固執せず、心的な投射を行わずにものごとをありのままに見ようとすることである。私たちが「私」「存在」と呼んでいるものは、各々が独立に、因果律に従い刻一刻と変化する物質的、心的要素の結合に過ぎない。そうした存在には、恒久で、永続し、不易で、永遠なものは何もない。(146‐147頁)
注4 『心を救うことはできるのか 心理学・スピリチュアリティ・原始仏教からの探究』 石川勇一 著 サンガ
ブッダは素朴な経験的な意味での自己(attan)は否定していません。むしろ自己をよりどころとして、自己を調えるように説きます。一方でその自己というものは、他の諸々の現象と同様に、無常であり、因縁によって生じているものであり、実体としては実在していません。自己は素朴な経験的な意味においては存在していますが、厳密な意味においては実在していないのです。自己はあるのでもなく、ないのでもない、ということなのです。(231頁)
今回の記事では、ブッダの重要な教え「無常・苦・無我」のうち、「無我」を取り上げました。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪
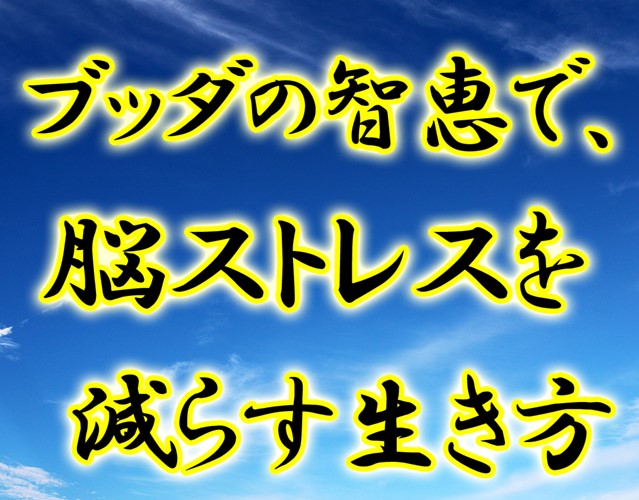
当ブログ管理人が書いた『ブッダの智恵で、脳ストレスを減らす生き方 最初に苦しみの矢を抜くための仏教入門』
Amazon Kindleで販売中です😊