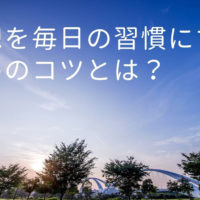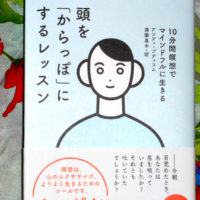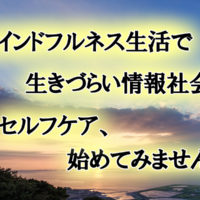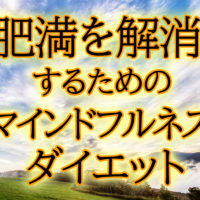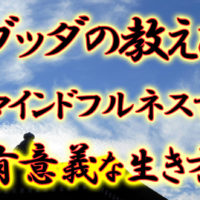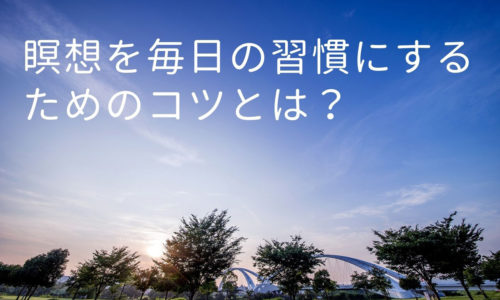contents

心身のバランスを整えたり、ストレスをやわらげたりするのに効果的な<マインドフルネス瞑想>を、いつまでも続ける生活習慣としてご自身のライフスタイルにとりいれてみませんか?
今回の記事では、マインドフルネス瞑想を始めるための方法、ポイントや注意点について述べていきます。
まず、マインドフルネス瞑想のやり方のポイントとしては、以下が挙げられます。
- 身体の力を抜いて楽な気持ちになる。
- 気持ちよく背筋を伸ばす。
- 呼吸にただ気づくようにする。
- 「いま」に意識を集中し、現在の時間を実況中継する。
- 判断を中立にする(心をニュートラルにする)。
- 雑念にとらわれたらサティ(気づき)の言葉を入れる。
- 瞑想のための時間をしっかりと取る。
マインドフルネスは、簡単に言うと、「今、ここ」にある練習です。
あなたの思考が、未来や過去にさまよっていることに気づいたら、今この瞬間に意識を向けていきます。
私たちは「今、ここ」にあるときと、「今、ここ」にないときがあります。というより、「今、ここ」にある時間より、未来のことを考えているか、過去のことを思い出していることがほとんどであることに気づくかもしれません。
マインドフルネスは繰り返し繰り返し、「今、ここ」に意識を向けていき、「今、ここ」にある時間を増やしていく取り組みです。
(吉田昌生『1分間瞑想法』 p46)
身体の力を抜いて楽な気持ちになる。

マインドフルネス瞑想を始める時は、まず、心地よい姿勢になり、体の力を抜いて気持ちを楽にします。
特にストレスを感じることが多い日常を送っていると、表情が険しくなり、呼吸は浅く、こめかみのあたりに余計な力が入っていることが多いので、体だけではなく頭部の辺りの力も抜いて、ゆるめていきましょう。
ちなみにマインドフルネス瞑想は座っていても寝ていても出来ますが、初めての場合は、座り心地の良い椅子や座布団の上に座ったり、楽な胡坐(あぐら)の姿勢になって始めてみると行いやすいです。
気持ちよく背筋を伸ばす
また、座って瞑想を始める時は、だらしなく座るのではなく、猫背にならないよう気持ちよく背筋を伸ばすことが大切です。
なぜなら、背すじを伸ばさないと、呼吸をした際に、気の通りが悪くなるからです。
背すじを気持ちよく伸ばし、肩の力を抜いて心地よい呼吸を行うと、身体の調子は良くなりますし、心もリフレッシュしていき、次第に気持ちも前向きになります。
ただ、呼吸に気づく。

姿勢が整ったら、実際にマインドフルネス瞑想を始めていきますが、まず大事なのは呼吸です。
最初のうちは目を閉じ、無理に「正しく呼吸しなくちゃ」と焦らず、自分のペースでと気持ちよく行うことが大切になってきます。
マインドフルネスでは呼吸をコントロールしようとせず、ゆったりと程度にとどめ、自然に呼吸を続けていきます。
現在の時間を実況中継する。

しばらくの間、自然に呼吸しながら、長いか短いか、深いか浅いかなど、気息の流れを観察していきます。
ゆったりと呼吸したくても、頭の中に様々な想念や雑念が浮かんできてしまう場合は、呼吸の流れを実況中継してみることがオススメです。
言葉を介さなくても構いませんが、息を吸う際に、空気が鼻腔のあたりを通り抜けていくのを感じながら、
「吸います、吸います、吸います」
また、鼻のちょうど下あたりで吐く息を感じながら、
「吐きます、吐きます、吐きます」
と実況中継すると、現在の時間に集中しやすくなります。
もし、だんだん退屈して気が散ってきたら、今度はお腹に手を当てて、その感覚をもとにして「ふくらみ、ふくらみ、ふくらみ」、「ちぢみ、ちぢみ、ちぢみ」と実況中継してみます。
マインドフルネス瞑想では判断を中立にする。

マインドフルネス瞑想をする目的のひとつは、自分の価値判断を一度、中立にすることだと言えます。つまり、感じたことや感覚に囚われるのではなく、客観的に観察するということなのです。
これはどういうことかといえば、普段、私たちは物事に対して、「好き/嫌い」「良い/悪い」「きれい/きたない」などと、自分の好き嫌いという認知の偏りや二分法的思考によって、一方的に価値判断してしまっています。
しかし、マインドフルネス瞑想をしている間だけは、自分の主観から離れ、頭のなかを一度リセットし、ニュートラルに、<世界>のあるがままの姿をあるがままに感じたり、観察したりするようにしてみるのです。
つまり、瞑想の最中は、自分がこれまで行ってきた判断をあえて宙づりにしてみるのです。
すると、自分がこれまで気づかなかった様々なことに気づける可能性が生じてきます。
雑念にとらわれたらサティ(気づきの言葉)を入れる。

では、しばらく呼吸を観察し、慣れてきたら、今度は視覚や聴覚など、五感で捉えられる様々な感覚をあるがままに感じてみましょう。
心をニュートラルにすると、音、匂い、色や光などが、これまでとは違った姿で現れてきます。
そして、ここでも「好き/嫌い」などと価値判断せず、水の音を感じたら、「水、水、水」、花の香りを感じたら、「花、花、花」など、サティ(気づき)を入れて、実況中継することで、再び主観によって判断してしまうのを避けましょう。
しかし、マインドフルネス瞑想を始めても、最初のうちは、すぐに雑念が浮かんできてしまいます。
特に嫌な出来事に直面した後や大きな失敗をやらかした直後では、その過去のことばかりが、頭に浮かんできてしまいます。
そのような場合は、「雑念、雑念、雑念」というサティを入れて、自分が雑念にとらわれていることに早めに気づくようにします。
また、過去のイヤな記憶や、他人の不愉快な言動を思い出して不快な気持ちになり、思わずイライラしてしまう時もあります。
そういう時は、そのイライラにずっとのみ込まれてしまうのではなく、時間がかかっても良いので、苛々や怒りにのみ込まれている自分に気づき、その苛々している自分を、一歩離れた場所から眺めるようにして、対象化してみましょう。
そして、雑念に気づいたら、また最初の「呼吸」への気づきに戻っていきましょう。
雑念にとらわれるのは当たり前。

しかし、雑念にとらわれるのは当たり前ですので、もし瞑想がなかなかうまくいかなくても、最初のうちは訓練だと思って、そのことで不必要に自分を責めたりしないでください。
それに加え、マインドフルネス瞑想をしている間に、過去の失敗や苦い思い出などが甦ってきても、その記憶を悪者扱いしたり、自分のせいにしたりすることで、自分にダメージを与えることは避けてください。
なぜなら、マインドフルネス瞑想を行う目的のひとつは、マイナスイメージの自分を否定せず、そのマイナスイメージの自分も、自分の一部として、ただ気づいたり、受け入れてあげたりするようになることでもあるからです。
瞑想のための時間をしっかりととる。

ほかには、マインドフルネス瞑想の効果をきちんと味わうための秘訣として、瞑想のための時間をしっかりと取ることを挙げてみます。
最初のうちは、何かの作業をしながら瞑想用のヒーリングミュージックを聴き、そのあいだ瞑想したつもりになったとしても、瞑想になっていない可能性が高く、その効果は半減してしまいます。
そのため、マインドフルネス瞑想を始めたばかりの時は、瞑想のための時間をきちんと確保し、仕事や勉強のこと、人間関係の悩み、スマホやメール、LINEのことなどは、その間、出来るだけ考えずに瞑想に取り組む姿勢が大切になってきます。
また、しばらくすると、脳が退屈だと思い始めますが、あえて退屈さを感じるということも、マインドフルネス瞑想を長く続けられるようになるための訓練のひとつです。
なお、気持ちよく瞑想を行うためには、最初のうちは都会の雑音を避けるために、川辺や海辺、静けさに満ちた森の中など、あえて瞑想に適した場所を選ぶことも必要です。
もし遠出できない場合は、自然の姿を撮影した高品質なYouTube動画を利用してみるのもオススメです。
マインドフルネス瞑想は地道に続けることが大切。

最後に、マインドフルネス瞑想はいきなりうまくやろうとしたり、すぐに何らかの分かりやすい効果を期待したりすることにそれほど意味はないように感じます。
それよりも、毎日瞑想のための時間を確保し、地道に少しずつ行うことで、意識が過去や未来だけではなく、現在の瞬間に向かうようトレーニングすることが重要なのです。
つまり、マインドフルネス瞑想とは、自分の心を拡張していく訓練なのであり、この心の訓練は、ウォーキングやジョギングのあいだ、食事中、掃除中など、様々な状況で応用してみることも可能です。
最初は10秒でも1分でも10分でもかまいませんので、もしマインドフルネス瞑想を途中であきらめずに、生活習慣として毎日続けていければ、世界がこれまでと違って見えるようになってきます。
そして、こころが満たされ、これまで気づくことができなかった(あるいは気づくことのなかった)世界の豊饒さにも気づけるようになります。
このことは、世界そのものが新しくなるのではなく、もともとあった世界の有り様に、<私自身>が気づくということでもあります。
試行錯誤しながらマインドフルネス瞑想を実践していく。
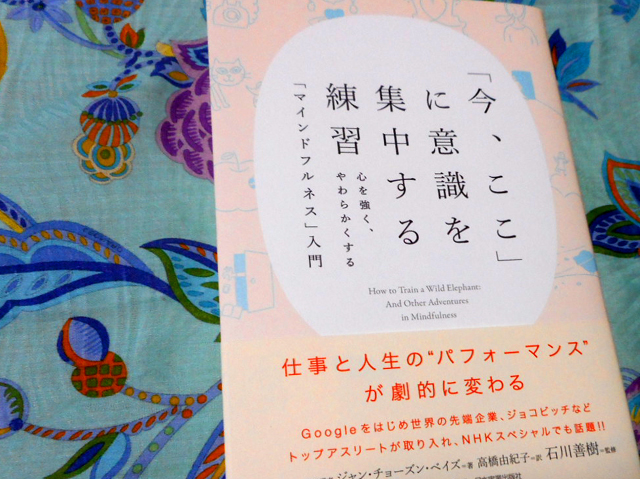
以上ここまで、マインドフルネス瞑想の方法のポイントについて最低限のことを書いてきましたが、この記事の内容はあくまで私自身が考えた目安ですので、100%正しいやり方であるというわけではありません。
そのため、マインドフルネス瞑想についてより詳しく知りたい方は、
- 『マインドフルネスストレス低減法』(ジョン・カバットジン 著)
- 『マインドフルネス入門講義』(大谷彰 著)
- 『ブッダの瞑想法 ヴィパッサナー瞑想の理論と実践』(地橋秀雄 著)
- 『『「今、ここ」に意識を集中する練習』(ジャン・チョーズン・ベイズ 著)
- 『自由への旅 「マインドフルネス瞑想」実践講義』(ウ・ジョーティカ 著)
- 『1日10秒マインドフルネス』(藤井英雄 著)
- 『1分間瞑想法』(吉田昌生 著)
など、マインドフルネス瞑想の入門書や上座部仏教に伝わるヴィッパサナー瞑想の方法について書かれた本が何冊も出版されていますので、参考までに何冊か読んでみることをオススメします。
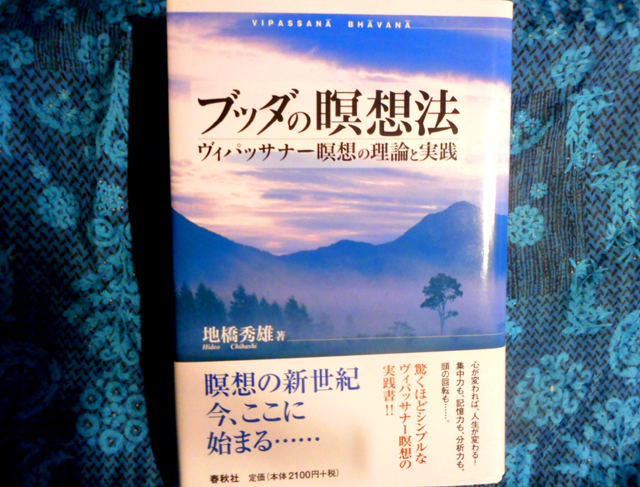
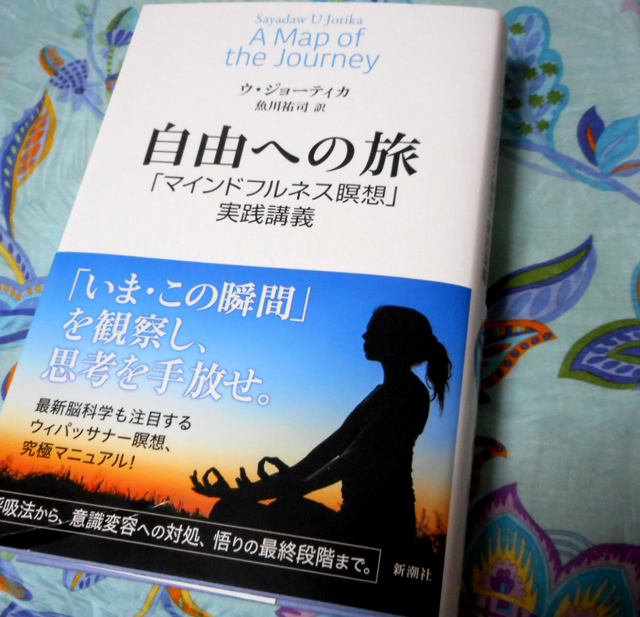
しかし重要なのは、やはり、本を読んで何でも分かったつもりになるのではなく、試行錯誤しながら、マインドフルネス瞑想を地道に実践していくことです。もちろん実際にマインドフルネス瞑想を行うイベントや講習会などに参加し、講師や指導者から直接やり方を教わってみるのもオススメです。
ここまで読んでくださり、ありがとうございます😊
当ブログ管理人が書いた『マインドフルネス習慣で「今・ここ」を選ぶ生き方 情報社会を生き抜くためのセルフケア』
AmazonのKindleストアで販売中です!!