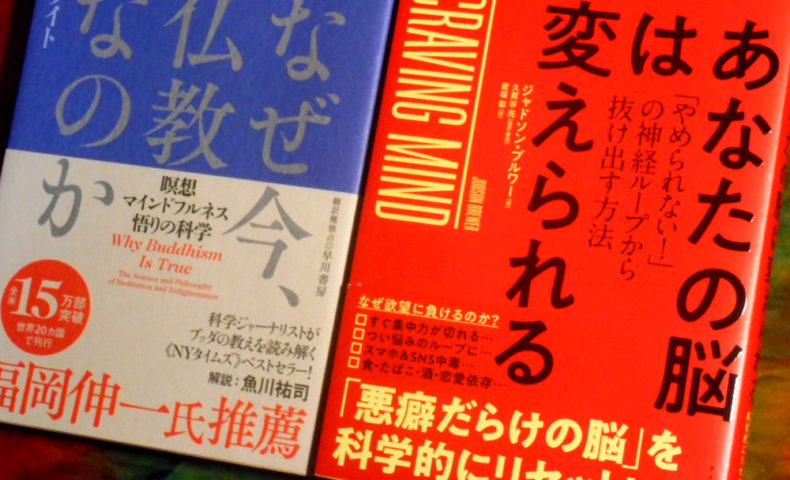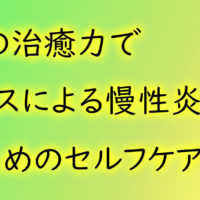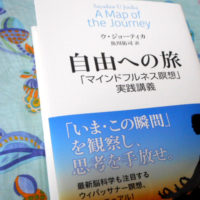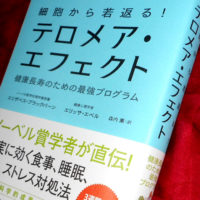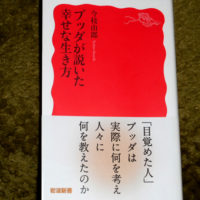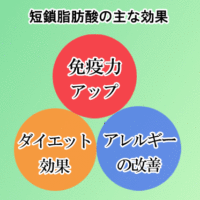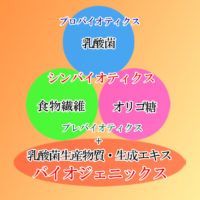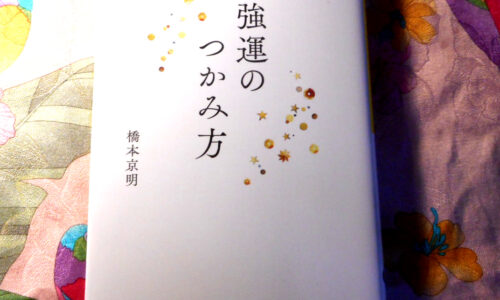contents
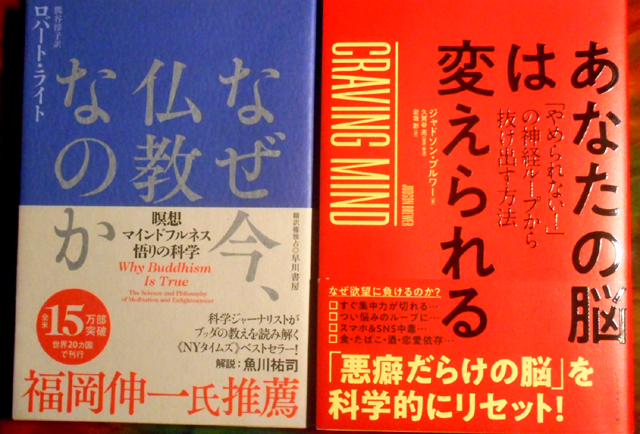
マインドフルネス瞑想を繰り返し練習することで、いつもの脳のパターンが変わる生き方、始めてみませんか?
先日【いつもの脳を変える生き方】として、
ということについて述べましたが、そもそも私たちの脳は長期的な利益よりも、目の前の報酬・ご褒美に弱く、最初から幸福な生き方が出来るように設計されてはいないことも事実です。
このことに関して、たとえば科学ジャーナリストのロバート・ライト氏は、以前の記事でも取り上げた『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』(熊谷淳子 訳)のなかで、「自然選択」について言及し、
私たちは自然選択によってつくられ、自然選択の仕事は遺伝子の繁栄を最大限に高まることにつきる。自然選択は、真実それ自体に頓着しないばかりか、私たちの長期的な幸せにも頓着しない。
かぶりつく前に放出されるドーパミンは、それを上まわる幸福が待っていると約束するものであり、かぶりついたあとのドーパミンの急降下は、ある意味で約束違反だ。少なくとも、過大な約束だったことを生化学的に認めているようなものだ。あなたもその約束をうのみにした――食べることそれ自体から得られる快楽より大きい快楽を期待した――という点で、妄想にかられたとはいわないまでも、少なくとも誤認させられたといえる。
残酷だといえなくもないが、自然選択に何を期待できるだろう。自然選択の仕事は遺伝子を拡散する機械をつくることだ。それが機械にある程度の錯覚を組みこむことを意味するなら、錯覚が組みこまれることになる。
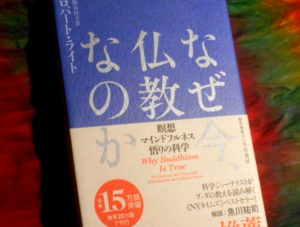
としています。
要するに、そもそも脳は進化と共に発達していったため、現実をあるがままに描写するようには最初から設計されていない、完璧ではないということがポイントなのです。
しかし、どういう感覚に対して「快」を感じるのか、もしくは「不快」を感じるのか、自分自身の内面や在りようと向き合うために、マインドフルネス瞑想(もしくは上座仏教におけるヴィパッサナー瞑想)を実践してみることは、特に様々な情報や刺激が溢れている現代社会に対しては、有効な処方箋になるように思うのです。
またこのことは、(本当は自分は何をしたいのかなど)自分自身への気づきを深めることにもつながるように思います。
マインドフルネス瞑想は繰り返し練習することで効果を発揮する。
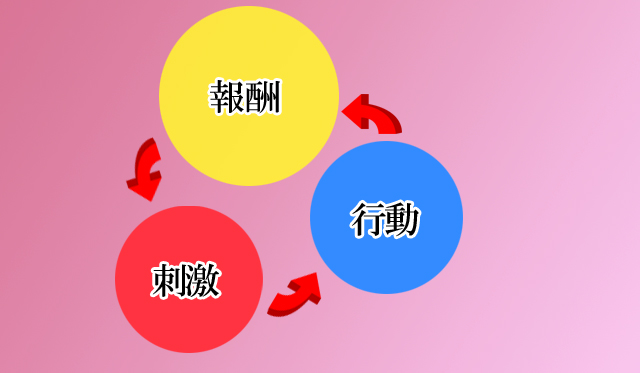
そして、スマホのゲームやSNSの情報などにふれるたび、刺激→行動→報酬といったいつものパターンで反応してしまうけれど結果的に心が満たされないという場合は、心の性質への対処法として、仏教の考え方や、「今・ここ」に気づくためのマインドフルネス瞑想や慈悲の瞑想を繰り返し練習していくことが重要になってくるように思うのです。
最新のスマホゲームにはまっているとき、あるいは好みの味のアイスクリームに病みつきになるとき、私たちは、現在科学的に知られているかぎりで、進化上最も古くから受け継がれている学習プロセスを働かせている。人間はそのプロセスを無数の生物種と共有する。最も原始的な神経系を持つ生物でも同じだ。それは、報酬に基づく学習プロセスである。
(ジャドソン・ブルワー『あなたの脳は変えられる』 岩坂 彰 訳 35頁)
このことに関してはロバート・ライト氏も、『なぜ今、仏教なのか』のなかで、
瞑想上達の道の大部分は、作用をおよぼしてくる原因に気づき、ものごとが自分をあやつる方法に気づくことであり、さらに、感覚がタンハーを生じさせる場所、快の感覚に対する渇望と不快の感覚に対する忌避を生じさせる場所に、連鎖のかなめとなる鎖があると気づくことだといっていいだろう。マインドフルネス瞑想が深く介入できるのはこの場所だ。
と述べています。
またそれは、
「十分に修養を積んだうえでの経験にもとづいた理解、マインドフルな気づきのことであり、それは連鎖を断ち切るか、少なくともゆるめるだけの力をもたらしてくれる」
としたうえで、
マインドフルネス瞑想の真の上達は、放っておくと勝手に知覚や思考や行動を方向づける感覚の力学への気づきをより深めること、そして、もとはといえばそのような感覚を引き起こす周囲のものごとへの気づきをより深めることを必然的に意味するといっていい。
とも述べています。
このようにマインドフルネス瞑想において大切なのは繰り返し練習することであり、もし途中で投げ出してしまえば、やはり結果的にいつもの刺激→行動→報酬のパターンや「もっともっと!」と欲しがるドーパミンに振り回される毎日に戻ってしまう可能性が高くなってしまうのです。
そしてほかの記事でも述べましたが、最初から1時間のマインドフルネス瞑想に挑戦するよりも、始めたばかりの頃はこまめに1分や10分実践したほうが、小さな習慣として続けやすくなります。
ちなみにいつもの脳を変えるのに最適なのはマインドフルネス瞑想以外では、神経可塑性の観点から、「運動」、特にヨーガや太極拳など、ゆっくりと動きつつ、瞬間瞬間に気づいていくための運動が挙げられます。
また、ウォーキングやジョギングなど適度に運動を行うことは、脳の様々な部位を複雑に刺激し、神経細胞を増やしたり、認知機能を改善したりすることにつながっていきますので、先日の記事で述べたスマホ脳の改善や、アルツハイマー病の予防にも効果的です。
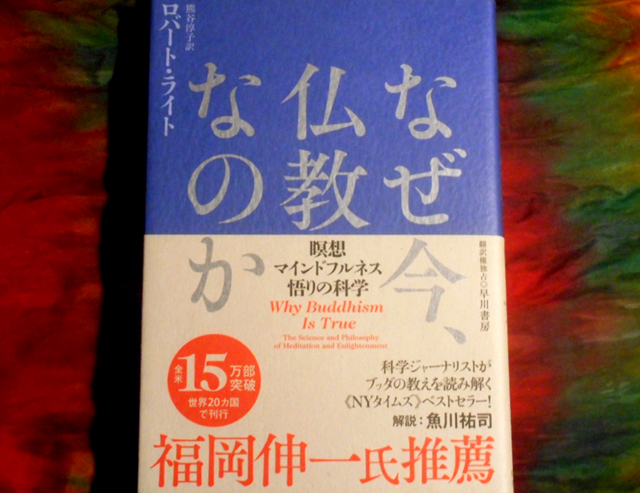
瞑想上達の道の大部分は、作用をおよぼしてくる原因に気づき、ものごとが自分をあやつる方法に気づくことであり、さらに、感覚がタンハーを生じさせる場所、快の感覚に対する渇望と不快の感覚に対する忌避を生じさせる場所に、連鎖のかなめとなる鎖があると気づくことだといっていいだろう。マインドフルネス瞑想が深く介入できるのはこの場所だ。
おそらく前の段落の「気づく」ということばには注釈をつけたほうがいいだろう。ここで私が言っているのは、このような因果の連鎖を観念的に理解する純粋に学問的な気づきのことではない。十分に修養を積んだうえでの経験にもとづいた理解、マインドフルな気づきのことであり、それは連鎖を断ち切るか、少なくともゆるめるだけの力をもたらしてくれる。
とはいえ、経験にもとづいた理解を補強し、ときに協働するのは、仏教哲学の一部をなす観念的な理解だ。マインドフルネス瞑想の真の上達は、放っておくと勝手に知覚や思考や行動を方向づける感覚の力学への気づきをより深めること、そして、もとはといえばそのような感覚を引き起こす周囲のものごとへの気づきをより深めることを必然的に意味するといっていい。仏教の悟りには西洋科学における啓蒙と共通する部分があるといえる。どんな原因がどんな結果をもたらすかという気づきをより深める必要がある点だ。
『なぜ今、仏教なのか 瞑想・マインドフルネス・悟りの科学』 ロバート・ライト 著 熊谷 淳子 訳 早川書房 270頁
今回はマインドフルネス瞑想は繰り返し練習することで効果を発揮するということについて述べてみました。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪
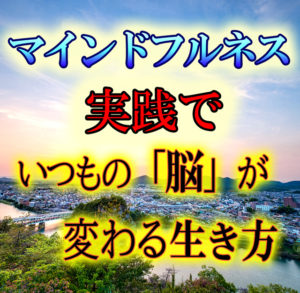
『マインドフルネス実践でいつもの「脳」が変わる生き方 もっと「今・ここ」を生きるための瞑想入門』
Amazon Kindle で販売中です😊