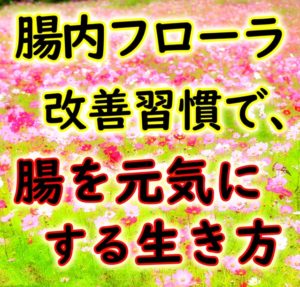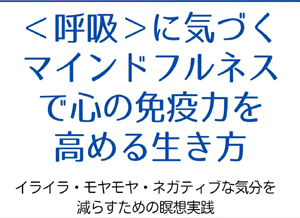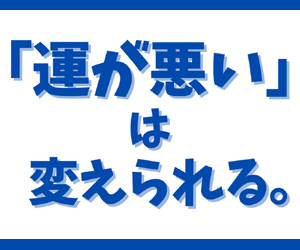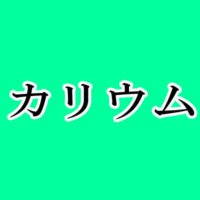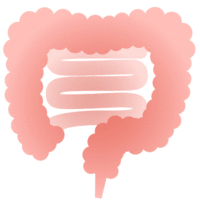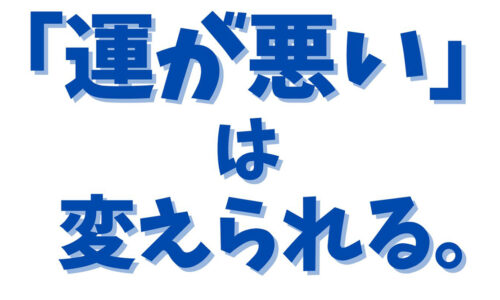contents

アレルギー改善やダイエット効果などが期待されている短鎖脂肪酸が、腸内細菌によってきちんと腸内で作られるようにすることは、いつまでも健康を維持していくために大切なことだと思われます。
そのため今回は、短鎖脂肪酸の効果・効能についてです。
短鎖脂肪酸とは腸内細菌が食物繊維やオリゴ糖などを原料にして作り出す飽和脂肪酸の一種で、酢酸、酪酸、プロピオン酸などの総称です。
この短鎖脂肪酸が腸内細菌によって生み出されると、免疫力のアップを中心に、健康に対して様々な効果がもたらされるとされています。
たとえば、医学博士の藤田紘一郎氏は、短鎖脂肪酸の効果・効能について以下を挙げています。
- 脂肪の蓄積を減らし、全身の代謝を活発にして肥満を防ぐ
- 糖尿病を直接的に改善するホルモン「インクレチン」を増やす
- アレルギー反応を抑えるTレグを増やす
- 脳内伝達物質であるセロトニンの分泌を促す
- 腸のバリア機能を高めることで、食中毒、炎症、食物アレルギー、動脈硬化、がんなどの病気を防ぐ
- 短鎖脂肪酸ができる過程で腸内細菌から水素が発生し、活性酸素を中和する
- 腸管の活動エネルギー源となる
(藤田紘一郎『腸内細菌が家出する日』より抜粋)
この短鎖脂肪酸は糖尿病を予防したり、余分な脂肪の蓄積を防いだりする効果があるため、生活習慣病の改善や痩せ菌ダイエットの救世主として、近年、メディアなどでも注目されるようになりました。
また、短鎖脂肪酸は以上のような効果だけではなく、抗炎症作用もあり、アレルギーやうつの症状の緩和することに加え、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患に対しても効果を発揮すると期待されています。
- 便の構成要素となり便量を増大し便秘を防ぐ
- 発がん物質や有害菌、有害物質を吸着し体外に排泄する
- 消化管の働きを活発にする
- 糖の吸収速度を遅くし食後の急激な血糖値上昇を防ぐ
- 唾液分泌を増す(咀嚼が多い場合)
- 胆汁酸を吸着し体外に排泄する
- コレステロールの余分な吸収を防ぐ
- ナトリウムの過剰を防ぐ
- 腸内での有用菌(善玉菌)のエサとなり有用菌を増やし腸内環境を改善する
- 胃袋がいっぱいになり過食しにくくなり、そのためカロリー制限できる
- 粘性の食物繊維ほど小腸に分泌される膵液と胆汁の液や酵素の量を多くする
- 腸の蠕動運動を活発にし、内容物を速やかに移動させる
- 水溶性食物繊維は短鎖脂肪酸をつくり、これがありとあらゆる作用をする
(鶴見隆史『食物養生大全』評言社 p420~421)
短鎖脂肪酸を増やすための方法とは?
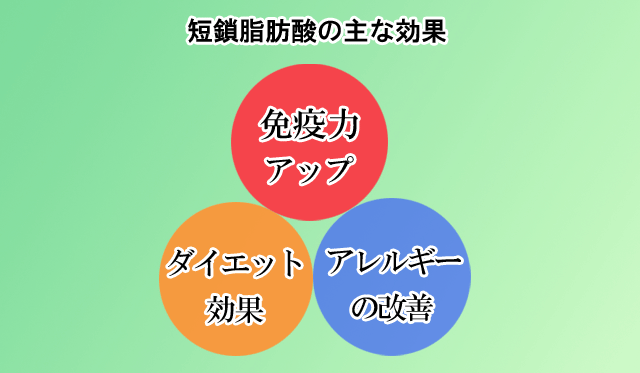
では短鎖脂肪酸を体内に増やしていくにはどうすれば良いのでしょうか?
その答えはやはり腸内細菌のバランスを整えて腸内環境や腸内フローラを改善していくことです。
特に、短鎖脂肪酸がきちんと作られるためには、腸内細菌のチームワークが大切だと、医学博士の藤田紘一郎氏は述べています。
つまり特定の乳酸菌だけに頼るのではなく、腸内細菌の多様性を大切にしながら、腸内環境を整えていくことが最も有効な手段なのです。
そのための具体的な方法としては、短鎖脂肪酸は食物繊維やオリゴ糖を摂ることで腸内細菌によって作られるため、普段から食物繊維(特に水溶性)やオリゴ糖が豊富に含まれた食材を適度に摂るようにして腸内フローラのバランスを整えたり、腸内環境を改善していったりすることが挙げられます。
以上、ここまで短鎖脂肪酸の効果・効能について述べてきましたが、腸内環境や腸内フローラの改善によって、ダイエットや免疫力アップ、アレルギーやうつの改善にも役立つとされる短鎖脂肪酸がきちんと作られるようにすることは、いつまでも健康を維持していくために大切なことだと思われます。
しかし、短鎖脂肪酸が腸内細菌による万能薬であるといっても、何事も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」で、短鎖脂肪酸を増やすことが目的で水溶性の食物繊維を過剰摂取し、腸内細菌を増殖させすぎてしまうことは、健康のために良くありません。
そのため、腸内環境を整える基本はやはり、土壌を耕すようなつもりで、適度に腸内細菌のバランスを整えることだと言えるのです。
短鎖脂肪酸とは、私たちが食べた食物繊維を腸内細菌が分解するときにつくる代謝産物だ。
腸内細菌がつくる主要な脂肪酸は三つ。酢酸、プロピオン酸、酪酸であり、排せつされるか結腸に吸収され、体の細胞のエネルギー源として使われる。
酪酸は結腸の内側をおおう細胞にとってもっとも重要な燃料であり、発がん抑制効果、抗炎症効果もある。
これらの脂肪酸の割合は腸内細菌の多様性や、食事のあり方に左右される。
(デイヴィッド・パールマター 『「腸の力」であなたは変わる』 白澤卓二 訳 p196)
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます(^^♪
『腸内フローラ改善習慣で、腸を元気にする生き方 「腸内細菌のバランスを整える」とは目的ではなく「結果」だった。』
Amazon Kindle で販売中です!!